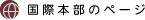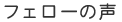|
|
第3回 埼玉県 行田市行田市は、さきたまの地。県名発祥の地として知られる埼玉県北部の町です。市の中心には、忍城(おしじょう)の掘割の面影を伝える水城公園や、復元された忍城御三階櫓があり、城下町の面影を伝えています。行田市の歴史の古さは、半端ではありません。市内に縄文・弥生の住居跡、9箇所の古墳群が確認されており、中でも、さきたま古墳群は、緑豊かな古墳公園として近隣の人々の憩いの場となっています。 行田散策の記夏の日の午後、城跡や古墳の公園に出かけてみました。ちょうど、「行田浮き城祭り」の日で、交通規制が始まる直前でした。行田市では、この外にも、戦国時代をテーマにした「忍城時代祭り」、古代をテーマにした「さきたま火祭り」があります。 忍城御三階櫓
忍城御三階櫓 蝉時雨がふりそそぐ忍城祉の公園内には、竹林や松や桜の大木が茂り、ひっそりとした気配が漂っていました。忍城は、秀吉の時代に石田三成の水攻めを受けましたが容易に落ちず、あたかも水に浮いているかのようだとのことから「浮き城」と呼ばれたということです。 現在の御三階櫓は、昭和になって復元されたもので、郷土博物館になっています。 藩校「進修館」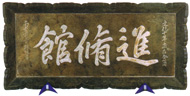
藩校「進修館」扁額 忍(おし)藩の藩校「進修館」は、元は松平忠翼が桑名において藩士の子弟育英のため設立したもので、文政6年松平氏の忍への移村に伴い移りました。現在の行田市でも、「進修館」から名前をいただいた漢学塾「進修塾」が運営されています。郷土の香 第1回で紹介されている三重県桑名市とは、姉妹都市が結ばれており、行政・民間の交流が今も盛んです。 また、行田市は、足袋の町としても知られています。江戸時代に始まった足袋の生産が、昭和の最盛期で全国生産の8割を占め、現在も約半数を生産しています。博物館の中には、足袋産業の資料とともに、お相撲さんに作った足袋が展示されていました。貴乃花や双子山親方、大鵬の足袋など、その大きさにビックリしました。中でも一番大きかったのは、曙関の足袋でした。 水城公園
夏の楽しみは 古代蓮池。 
何時行っても 忍城の外堀の沼を利用した公園です。自宅から車で数分なので、時々、気分転換に一巡りします。季節によってツツジ、ショウブ、アジサイなどの花が楽しめます。今日は、古代蓮池の蓮が、涼しそうでした。 さきたま古墳公園 
二子山古墳の前には、 水城公園から車で数分のところには、埼玉県名発祥の碑がある「さきたま古墳公園」があります。 
古代をテーマにした さきたま火祭り。 古代蓮の里 ごみ焼却場建設の折、偶然発芽したのが発見された行田蓮(古代蓮)。約1400年から3000年前の蓮と言われています。この蓮にちなんだ古代蓮の里には、41種類10万株の蓮が植えられており、7月の初旬から8月の中旬には、この蓮を見に遠方からも大勢の方がいらっしゃいます。 行田名物 フライとゼリーフライ行田名物として、代表的なのが フライとゼリーフライ。 
「かねつき堂」というフライのお店 
東照宮 「かねつき堂」という店の名前の由来は、隣接している東照宮の鐘楼が取り壊される時に、店主が移転したことによるとのことでした。  これがフライ。フライといっても、揚げ物ではなく、焼き物なのです。お好み焼きに似ていますが、大阪のような実沢山ではありません。昭和初期に足袋工場で働く女性の間で人気を集めたものが、名物として定着したということです。  お皿に載っているコロッケのようなものが、ゼリーフライ。形が銭のようなので、銭フライと呼ばれていたとの説もあります。おから入りコロッケという感じです。 蔵の街のお菓子屋さん 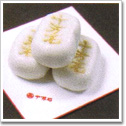 忍藩の十万石にちなんだ「十万石ふくさや」本店の店構えは、江戸時代後期の店蔵。元は呉服店が建設したもので、その後は足袋倉庫として使われたこともあったそうです。国の重要文化財に指定されています。 (広報・編集委員 佐藤 恭子 記)
|
 |